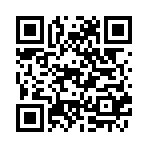2008年06月19日
ムカデ(百足)
 朝からグロくてすいません。
朝からグロくてすいません。ムカデの襲撃に遭いました。すぐに撃退しましたが、軽く右手首の上に被害。
くそぉ~ムカデめぇ…。とんがり山を離れた時から、もう襲撃に遭う事なんか有り得無いと勝手に思い込んでいましたが、埼玉の田舎にはまだまだ隠れ住んでいました。
ムカデに隙を見せてしまった…無念。
ムカデ詳細
※出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特徴
現在は、増節変態をする改形亜綱のゲジ目、イシムカデ目、ナガズイシムカデ目(日本未産)と、一般に雌雄同形で自由生活ステージでは変態しない整形亜綱のジムカデ目、オオムカデ目に分類される。狭義のムカデはオオムカデ目のトビズムカデやイシムカデ目のイッスンムカデなど人目につきやすいいわゆるムカデ型の生物を指すが、広意にはゲジや微小な土壌動物なども含む。
ムカデ類の体は頭部と歩肢の並んだ胴部からなる。頭部には1対の触角と口器がある。頭部の次の体節には、歩肢がなく、その代わりに顎の形になった顎肢がある。全てのムカデは顎肢に毒腺を持ち、この毒を用いて昆虫などの動物を捕食する。 それに続く体節には、それぞれ1対の歩肢がある。歩肢の数は分類群によって異なり、イシムカデ目、ゲジ目の成体は15対、オオムカデ目では21又は23対、ジムカデ目では種によって異なり27対から37対、41対、47対などを示し多い種は100対を越し173対まである。ジムカデの歩肢対数には多くの個体変異がみられるが、発生による制約があるらしく偶数対の歩肢対をもつ個体は稀な奇形である。最後の節には1対の尾脚=曳航肢と、改形類の雌では生殖肢がある。
どの種も肉食で、小動物を捕食する。オオムカデ類はヒトに対して能動的に攻撃をかけるものがあり、噛まれるとかなり痛む。人命に係る被害はほとんど無いが、南米に産する最大級のオオムカデ(ペルーオオムカデまたはペルビアンジャイアントと呼ばれている)は400mmに達し、幼児の被害や首などの急所を咬まれた場合には例外的に死亡の報告もある。他に鼻孔などから侵入したムカデが副鼻腔内で生存して慢性的な疾患の病原となる事例が知られている。なお、日本国内に於いては、漁船の船長が操舵手として操船中に船内にいたムカデに指を咬まれ一時意識を喪失して消波ブロックに衝突する事故が発生した事例報告がある。しかし、ムカデの咬害により死亡した例は報告されていない。大型種の多くは人間による拘束状況下において狂暴で触れたものには手当たりしだいに噛み付く。
[編集] 生息環境
小型のものは土壌動物として生活しているものが多い。イシムカデ類は、比較的短い体形で軽快に走り回り小動物を捕らえる。地中に棲む傾向の強い種は単眼数が少なかったり無眼の場合もあり、淡い体色で体毛が少なく肢や触角が短い。地中(朽木を含む)生活に特化したジムカデ類は無眼で黄色や赤、白、緑などの体色を示し、非常に細長い体に短い足を多数持ち、土壌中をミミズのようにはい回る。つつくと尾端を頭部と擬態して後ずさりしたりとぐろを巻くように体を丸める種が知られている。地下5mほどの餌となる土壌生物の密度が薄い層からも得られることがあり、活発な垂直移動をしていると思われる種もある。また、発光生物として知られている数種を含んでいる。オオムカデ類もほとんどの小型種は無眼で土壌動物である。一部の大型種は4個程度の単眼を持ち樹上などを徘徊して獲物を襲って食べる、この仲間に日本本土最大の種「アカズムカデ」が含まれる。特に大型のものはセミのような大型で活発な昆虫やネズミ[1]、コウモリ[2]さえ補食することが知られている。ゲジ類は長い歩肢と複眼や背面の大きな気門などにより徘徊生活に特化しており、樹上での待ち伏せでは長い脚を空中に巡らせて飛行中の蛾などを採食している。
[編集] 人間の生活との関わり
主に夏場、山林に近い民家では、ゴキブリなどを捕食するためにムカデがしばしば家屋の内部に侵入する。この場合、靴の中や寝具に潜んだりすることから咬害が多く、衛生害虫としても注意が必要である。
産業との関連は少ない。近年の日本では不快害虫の忌避効果を目的とした薬剤にムカデ・ヤスデの侵入防止効果を謳う場合が多い。オオムカデ類の油漬けや乾物は火傷や切り傷に効果があるとされ、民間薬として知られており、一部に市販の例もある。韓国では干したオオムカデを鶏の腹に詰めて煮込む薬膳がある。漢方では生薬名を蜈蚣(ごしょう)といい、平肝・止痙・解毒消腫の効果があるとされる。こうした薬用の意図の無い一般の食用とされた報告は皆無。観賞魚などの餌として冷凍のオオムカデが輸入されて市販されている。昆虫やクモ、サソリなどがかなり頻繁にアクセサリーやグラフィックのモチーフになることに比べるとムカデについては僅少な例しか無い。ペット(広意)としての飼育は、輸入種を中心に拡大傾向にある。現在、さまざまな種類が入荷しており大型種ほど高値で販売されている。
家庭用殺虫剤等では急ぐには死なない(近年はムカデ用の殺虫剤が市販され、冷却により動きを止め効果の解り易さを演出している)。
「非常に凶暴で攻撃性が高い」というイメージや、「絶対に後ろに下がらない(後退しない)」という俗信から、戦国時代にはムカデにあやかり甲冑や刀装具等にムカデのデザインを取り入れたり(伊達政宗の従兄弟、伊達成実が兜の前立とした事は有名である)、旗差物にムカデの絵を染め抜いた物を用いた武将もいた。武田家の金堀り衆は、トンネル戦法を得意とする工兵部隊で百足衆と呼ばれたとも言われる。相馬中村藩に起源する相馬野馬追においては「下がりムカデ」の旗が軍師の指物と指定されている。足の多いことにより、伝令をムカデに例えることも一般的。
赤城山などの神体として、また『毘沙門天』の使いとされ神格化されている。男体山の大蛇と日光の戦場ヶ原で決闘した伝説、藤原秀郷(俵藤太)の百足退治伝説などが知られる。大蛇が河川を象徴し砂鉄の採集や製鉄の技術者集団を表すことと比して、ムカデは地下坑道を掘り進み自然金などの鉱石を採集する技術者集団を表しているという説がある。
現在は、増節変態をする改形亜綱のゲジ目、イシムカデ目、ナガズイシムカデ目(日本未産)と、一般に雌雄同形で自由生活ステージでは変態しない整形亜綱のジムカデ目、オオムカデ目に分類される。狭義のムカデはオオムカデ目のトビズムカデやイシムカデ目のイッスンムカデなど人目につきやすいいわゆるムカデ型の生物を指すが、広意にはゲジや微小な土壌動物なども含む。
ムカデ類の体は頭部と歩肢の並んだ胴部からなる。頭部には1対の触角と口器がある。頭部の次の体節には、歩肢がなく、その代わりに顎の形になった顎肢がある。全てのムカデは顎肢に毒腺を持ち、この毒を用いて昆虫などの動物を捕食する。 それに続く体節には、それぞれ1対の歩肢がある。歩肢の数は分類群によって異なり、イシムカデ目、ゲジ目の成体は15対、オオムカデ目では21又は23対、ジムカデ目では種によって異なり27対から37対、41対、47対などを示し多い種は100対を越し173対まである。ジムカデの歩肢対数には多くの個体変異がみられるが、発生による制約があるらしく偶数対の歩肢対をもつ個体は稀な奇形である。最後の節には1対の尾脚=曳航肢と、改形類の雌では生殖肢がある。
どの種も肉食で、小動物を捕食する。オオムカデ類はヒトに対して能動的に攻撃をかけるものがあり、噛まれるとかなり痛む。人命に係る被害はほとんど無いが、南米に産する最大級のオオムカデ(ペルーオオムカデまたはペルビアンジャイアントと呼ばれている)は400mmに達し、幼児の被害や首などの急所を咬まれた場合には例外的に死亡の報告もある。他に鼻孔などから侵入したムカデが副鼻腔内で生存して慢性的な疾患の病原となる事例が知られている。なお、日本国内に於いては、漁船の船長が操舵手として操船中に船内にいたムカデに指を咬まれ一時意識を喪失して消波ブロックに衝突する事故が発生した事例報告がある。しかし、ムカデの咬害により死亡した例は報告されていない。大型種の多くは人間による拘束状況下において狂暴で触れたものには手当たりしだいに噛み付く。
[編集] 生息環境
小型のものは土壌動物として生活しているものが多い。イシムカデ類は、比較的短い体形で軽快に走り回り小動物を捕らえる。地中に棲む傾向の強い種は単眼数が少なかったり無眼の場合もあり、淡い体色で体毛が少なく肢や触角が短い。地中(朽木を含む)生活に特化したジムカデ類は無眼で黄色や赤、白、緑などの体色を示し、非常に細長い体に短い足を多数持ち、土壌中をミミズのようにはい回る。つつくと尾端を頭部と擬態して後ずさりしたりとぐろを巻くように体を丸める種が知られている。地下5mほどの餌となる土壌生物の密度が薄い層からも得られることがあり、活発な垂直移動をしていると思われる種もある。また、発光生物として知られている数種を含んでいる。オオムカデ類もほとんどの小型種は無眼で土壌動物である。一部の大型種は4個程度の単眼を持ち樹上などを徘徊して獲物を襲って食べる、この仲間に日本本土最大の種「アカズムカデ」が含まれる。特に大型のものはセミのような大型で活発な昆虫やネズミ[1]、コウモリ[2]さえ補食することが知られている。ゲジ類は長い歩肢と複眼や背面の大きな気門などにより徘徊生活に特化しており、樹上での待ち伏せでは長い脚を空中に巡らせて飛行中の蛾などを採食している。
[編集] 人間の生活との関わり
主に夏場、山林に近い民家では、ゴキブリなどを捕食するためにムカデがしばしば家屋の内部に侵入する。この場合、靴の中や寝具に潜んだりすることから咬害が多く、衛生害虫としても注意が必要である。
産業との関連は少ない。近年の日本では不快害虫の忌避効果を目的とした薬剤にムカデ・ヤスデの侵入防止効果を謳う場合が多い。オオムカデ類の油漬けや乾物は火傷や切り傷に効果があるとされ、民間薬として知られており、一部に市販の例もある。韓国では干したオオムカデを鶏の腹に詰めて煮込む薬膳がある。漢方では生薬名を蜈蚣(ごしょう)といい、平肝・止痙・解毒消腫の効果があるとされる。こうした薬用の意図の無い一般の食用とされた報告は皆無。観賞魚などの餌として冷凍のオオムカデが輸入されて市販されている。昆虫やクモ、サソリなどがかなり頻繁にアクセサリーやグラフィックのモチーフになることに比べるとムカデについては僅少な例しか無い。ペット(広意)としての飼育は、輸入種を中心に拡大傾向にある。現在、さまざまな種類が入荷しており大型種ほど高値で販売されている。
家庭用殺虫剤等では急ぐには死なない(近年はムカデ用の殺虫剤が市販され、冷却により動きを止め効果の解り易さを演出している)。
「非常に凶暴で攻撃性が高い」というイメージや、「絶対に後ろに下がらない(後退しない)」という俗信から、戦国時代にはムカデにあやかり甲冑や刀装具等にムカデのデザインを取り入れたり(伊達政宗の従兄弟、伊達成実が兜の前立とした事は有名である)、旗差物にムカデの絵を染め抜いた物を用いた武将もいた。武田家の金堀り衆は、トンネル戦法を得意とする工兵部隊で百足衆と呼ばれたとも言われる。相馬中村藩に起源する相馬野馬追においては「下がりムカデ」の旗が軍師の指物と指定されている。足の多いことにより、伝令をムカデに例えることも一般的。
赤城山などの神体として、また『毘沙門天』の使いとされ神格化されている。男体山の大蛇と日光の戦場ヶ原で決闘した伝説、藤原秀郷(俵藤太)の百足退治伝説などが知られる。大蛇が河川を象徴し砂鉄の採集や製鉄の技術者集団を表すことと比して、ムカデは地下坑道を掘り進み自然金などの鉱石を採集する技術者集団を表しているという説がある。
Posted by とんがり山 at 10:01│Comments(3)
│なんでやねん!?
この記事へのコメント
こないだ 窓を開けようとしたら サンのとこに
挟まれてすでに絶命した 百足がいて びっくり
更に 亀岡で 山仕事するのに 長靴借りたら
脱いだとたん 百足が出てきて びっくり
お陰様で 難は逃れています(今のところ)
挟まれてすでに絶命した 百足がいて びっくり
更に 亀岡で 山仕事するのに 長靴借りたら
脱いだとたん 百足が出てきて びっくり
お陰様で 難は逃れています(今のところ)
Posted by みかぶぉん at 2008年06月19日 11:48
at 2008年06月19日 11:48
 at 2008年06月19日 11:48
at 2008年06月19日 11:48ムカデは嫌いだ。
Posted by とんがり山 at 2008年06月19日 19:58
at 2008年06月19日 19:58
 at 2008年06月19日 19:58
at 2008年06月19日 19:58今の家(とんがり山の近く)に引っ越してきたとき
鳩の鳴き声と虫の多さにビックリしました。
もちろん今でも虫は大嫌いです。
鳩の鳴き声と虫の多さにビックリしました。
もちろん今でも虫は大嫌いです。
Posted by いわし at 2008年06月19日 20:54